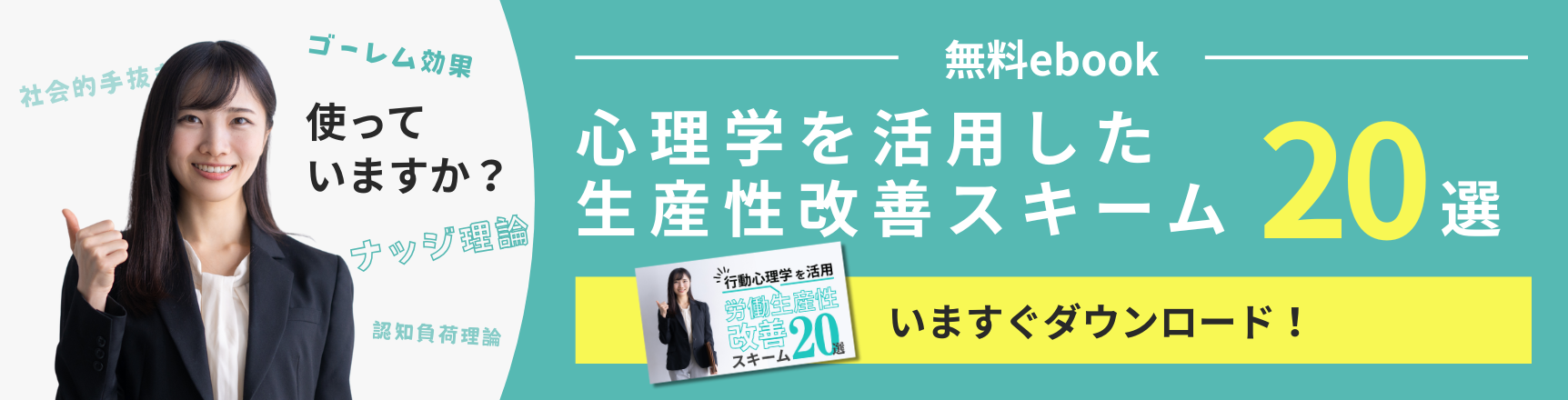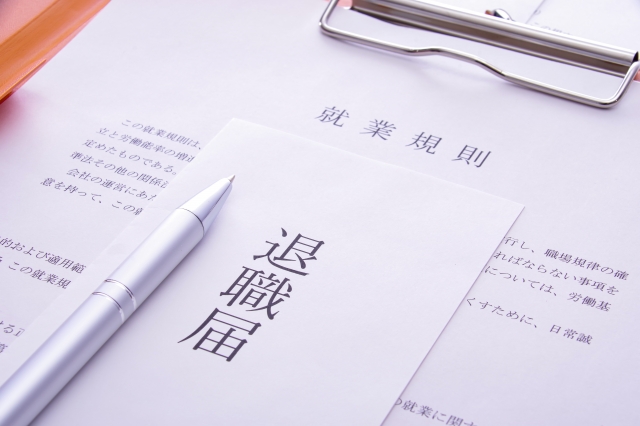人手不足は多くの企業が直面している深刻な課題です。求人を出しているのに応募が集まらない、せっかく採用しても定着しないといった悩みを抱えている経営者や採用担当者は数多く存在します。このような状況は企業の成長を阻害し、既存の従業員の負担も増していきます。
実は、求人が上手くいかない背景には、時代の変化に対応できていない求人内容や、ターゲット設定の甘さなど、具体的な原因が隠れています。
本記事では、求人を出しても人が来ない理由から、人手不足を解消するための具体的な方法まで、実践的な解決策をお伝えします。記事を読むことで、採用がうまくいかない本当の理由を理解でき、今すぐに実行できる改善策を手に入れられるでしょう。
目次
Toggle求人を出しても人が来ない主な原因
企業が求人を出しても応募が集まらない状況は、決して運の問題ではありません。むしろ、求人戦略や企業の体質に関わる明確な理由が存在しています。
ここからは、人手不足に陥る主な原因を3つの視点から解説します。これらの原因を把握することで、自社の採用活動における問題点を特定しやすくなるでしょう。
また、原因を理解することで、どのような改善策が必要か見えてくるようになるでしょう。採用に関連する課題は複合的に作用することが多いため、複数の原因が存在する可能性も考慮しながら読み進めてください。
求人内容が時代に合っていない
現在の求職者の価値観や働き方に対する考え方は、数年前とは大きく変わっています。労働条件だけを並べた従来型の求人では、今の人材の心には響きにくくなってきています。例えば、給与額だけを前面に出し、職場の雰囲気や成長機会についての記載がない求人は、若い世代を中心に敬遠されがちです。
また、リモートワークやフレックス勤務などの柔軟な働き方を求める人材は増加しており、こうした要素を記載していない求人は競争力を失っています。さらに、企業の社会的責任やビジョンに共感できるかどうかも、求職者の判断材料となっています。
つまり、求人原稿を作成する際には、数字だけでなく、企業としての姿勢や職場環境を伝えることが重要だといえるでしょう。
求人媒体の選定ミス
求人を出す媒体の選択も、応募数を左右する要因です。求人サイトはそれぞれ異なるユーザー層を抱えており、媒体によって年齢層や職業経験、価値観なども異なっています。営業職や事務職を募集する場合と、専門技術を持つ人材を募集する場合では、利用すべき媒体が異なります。
また、スマートフォンを中心に求職活動を行う層と、パソコンを主体とする層でも、アクセスする媒体に違いが出ます。加えて、同じ職種であっても年代によって利用する求人サイトが異なるため、求める人材がどのような媒体を使用しているか事前に調査することが欠かせません。
自社の人材ニーズに合わない媒体を選んでしまうと、どれだけ良い求人原稿を作成しても、ターゲットにたどり着きません。この選定ミスが、応募が集まらない主な原因の1つになりかねません。
社内の労働環境・離職率に課題がある
求人に応募が集まっていても、採用後の定着率が低い場合は、社内の労働環境や職場文化に問題がある可能性が高いです。どんなに優れた人材を採用しても、入社後の環境が良くなければ、すぐに離職してしまいます。
このような企業は、口コミサイトなどに負の情報が蓄積され、それが新たな求職者に伝わることで、求人への応募数がさらに減少していくという悪循環に陥ります。労働時間が長すぎる、上司や同僚との人間関係に問題がある、給与面での不公正感が存在するなど、離職の背景にある原因は多岐にわたります。
求人を出しても人が来ない状況に陥っている企業の多くは、実は内部の問題に対処せずに、外部への求人活動だけに注力してしまいがちです。
人手不足を解消する求人方法
人手不足を解消するには、求人戦略そのものを見直す必要があります。ここからは、実際に企業が実施できる3つの具体的な方法を紹介します。これらの方法を組み合わせることで、応募の質と量を向上させることができます。
同時に、自社に適した人材を確保する可能性も高まるでしょう。重要なのは、一度に全てを実行するのではなく、自社の状況に応じて優先順位をつけながら進めることです。
ターゲットを明確にする
求人を出す際に最初に必要な作業は、採用したい人材像を明確に定義することです。ターゲットが曖昧な求人は、採用担当者の理想と求職者の期待にズレが生じやすく、マッチング率が低下してしまいます。具体的には、年齢層、職務経歴、スキルレベル、性格特性、価値観といった要素を詳細に設定することが重要です。
また、必須要件と歓迎要件を分けて記載することで、より多くの候補者にアプローチできるようになります。さらに、ターゲットが決まれば、どの求人媒体を使用すべきか、どのような表現で求人原稿を書くべきかも自動的に決まってきます。つまり、ターゲット設定は、その後の採用戦略全体の基盤となる極めて重要なステップといえるでしょう。
求人原稿の書き方を見直す
ターゲットが明確になった後は、求人原稿の内容を見直すことが必要です。従来の求人原稿は、職務内容と給与条件を中心に書かれることが多かったのですが、現在の求職者は企業文化や働き方、成長機会といった要素を重視する傾向にあります。
求人原稿では、仕事内容を具体的に記載するだけでなく、その仕事を通じてどのような成長ができるのか、チーム内でどのような人間関係が築けるのか、といった点に触れることが効果的です。
また、企業の理念やビジョン、社会への貢献について簡潔に伝えることで、求職者との共感を生み出しやすくなります。さらに、数字で表現できる情報は可能な限り具体的に記載し、読み手が職場をイメージしやすくするための工夫も大切です。
他社より「働きやすさ」を明確に打ち出す
競争が激しい採用市場では、他社との違いを明確に示すことが不可欠です。働きやすさという要素は、現在の求職者にとって極めて重要な判断基準となっています。
例えば、残業時間の削減に取り組んでいる、育児と仕事の両立支援制度が充実している、リモートワークが導入されているなど、具体的な働きやすさを求人原稿に盛り込むことで、求職者の興味を引き出せます。
加えて、既存の従業員からの推薦制度を活用することで、企業の働き方や環境についての信頼性の高い情報が求職者に伝わります。働きやすさを打ち出すことは、採用活動のみならず、離職防止にも効果があるため、企業全体の人材戦略として重視する価値があるといえるでしょう。
人手不足解消に役立つ採用チャネル・ツール例
現在、求人活動に活用できるツールや媒体の種類は多岐にわたります。
ここからは、特に効果的な3つの採用チャネルとツールを紹介します。各ツールには異なる特性があるため、自社の採用ニーズに応じて選択することが重要です。これらのツールを組み合わせることで、採用の成功確率を高めることができるでしょう。
①スタンバイ|SNSとの連携が強くスマホ世代に効果的な求人サイト
スタンバイは、株式会社スタンバイ(ビズリーチグループ)が運営する総合求人プラットフォームで、SNSとの連携機能に強みを持っています。X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどの主要SNSと連携し、求人情報を自然な形で拡散できるのが大きな特徴です。
特にスマートフォンを中心に求職活動を行う20〜30代の若年層にとっては、SNS上で気軽に求人情報を目にできるため、応募のハードルが下がります。企業側は、求人ページを作成するだけで複数の媒体に自動掲載できるため、宣伝コストを抑えつつ高い拡散力を得られます。
また、スタンバイはIndeedやGoogleしごと検索とも連携しており、検索結果への表示範囲が非常に広い点も魅力です。管理画面では応募数や閲覧数をリアルタイムで確認でき、効果測定や求人内容の改善もワンクリックで実施可能です。
スマートフォン最適化された操作画面は、通勤中や休憩時間に求人を閲覧するユーザーにも快適で、応募までの導線が短いため、応募率が高い傾向があります。スタンバイを活用することで、特に若年層へのアプローチとSNS経由の自然流入を同時に実現できます。
②HRMOS採用|「欲しい」人材を確保できる採用管理システム
HRMOS採用(ハーモス採用)は、株式会社ビズリーチが提供するクラウド型採用管理システム(ATS)です。応募受付から内定承諾までのプロセスをすべてオンラインで一元管理できるため、採用担当者の作業負担を大幅に軽減します。
最大の特徴は、「応募者情報の自動集約」と「選考進捗の可視化」です。複数の求人媒体から流入した応募者情報を自動で取り込み、採用進行状況を一覧で確認できます。メールのやり取り、面接スケジュール調整、評価の共有なども同一画面で完結するため、担当者間の情報共有ミスを防げます。
さらに、AIによる候補者スコアリング機能が搭載されており、過去の採用データをもとに自社が求める人材像とマッチする応募者を自動で抽出します。これにより、感覚的な判断ではなくデータに基づいた精度の高い採用活動が可能になります。
ダッシュボード上では採用コスト・面接通過率・求人別応募数などが自動集計され、採用戦略の見直しにも役立ちます。中途採用・新卒採用・アルバイト採用など、あらゆる雇用形態に対応している点も魅力です。
出典参照:採用できる採用管理システム「HRMOS(ハーモス)採用」|株式会社ビズリーチ
③Wantedly|「共感採用」に強いSNS型採用プラットフォーム
Wantedly(ウォンテッドリー)は、従来の「条件マッチ型」ではなく、「共感マッチ型」の採用を実現するSNS型プラットフォームです。企業のビジョンやカルチャー、メンバーの想いなどを丁寧に発信できる仕組みが整っており、単なる求人媒体ではなく、企業ブランディングと採用を一体化できる点が最大の魅力です。
求人ページには、写真・動画・社員インタビューなどを掲載でき、求職者に会社の雰囲気を直感的に伝えられます。また、フォロワー機能を通じて企業の最新情報を発信できるため、長期的なファンづくりにもつながります。
さらにWantedlyでは「カジュアル面談」という文化が根付いており、選考前に求職者とフランクに会話できるのも特徴です。これにより、応募者の価値観や志向を深く理解でき、ミスマッチを防ぎながら採用の精度を高めることが可能です。
企業向けのダッシュボードでは、閲覧数や応募経路、面談率などのデータを可視化でき、効果的な求人改善につなげられます。特に、スタートアップやベンチャー企業、カルチャー重視の組織にとっては、Wantedlyが理想的な採用ツールといえるでしょう。
出典参照:共感でつながるビジネスSNS Wantedly|ウォンテッドリー株式会社
求人を出しても人が来ない!とお悩みの方は『CLOUD BUDDY』へご相談ください
求人を出しても人が来ない!とお悩みの方は『CLOUD BUDDY』へご相談ください
求人を出しても人が来ない状況は、適切な対策を講じることで改善していきます。しかし、問題の原因が複雑であったり、社内の労働環境改善が必要であったりする場合は、外部の専門家の支援を受けることも検討する価値があります。
『CLOUD BUDDY』は、採用戦略の設計から求人原稿の作成、さらには採用チャネルの最適化まで、採用活動全般に関わる総合的なサポートを提供しています。自社の採用課題に対して、具体的で実行可能な解決策を一緒に構築することで、人手不足の解消を目指しましょう。
まとめ|人手不足を解消できる求人やツールを活用しよう
人手不足は多くの企業にとって避けられない課題ですが、適切な対策により十分に改善の余地があります。求人内容の見直し、ターゲットの明確化、そして自社に適した採用チャネルの活用により、応募の質と量を向上させることができるでしょう。同時に、社内の労働環境整備にも目を向けることで、採用後の定着率を高めることにつながります。
本記事で紹介した方法やツールを参考にしながら、自社の採用戦略を立案し、実行に移しましょう。人手不足という課題を乗り越えることで、企業の持続的な成長と従業員の満足度向上を実現させてください。