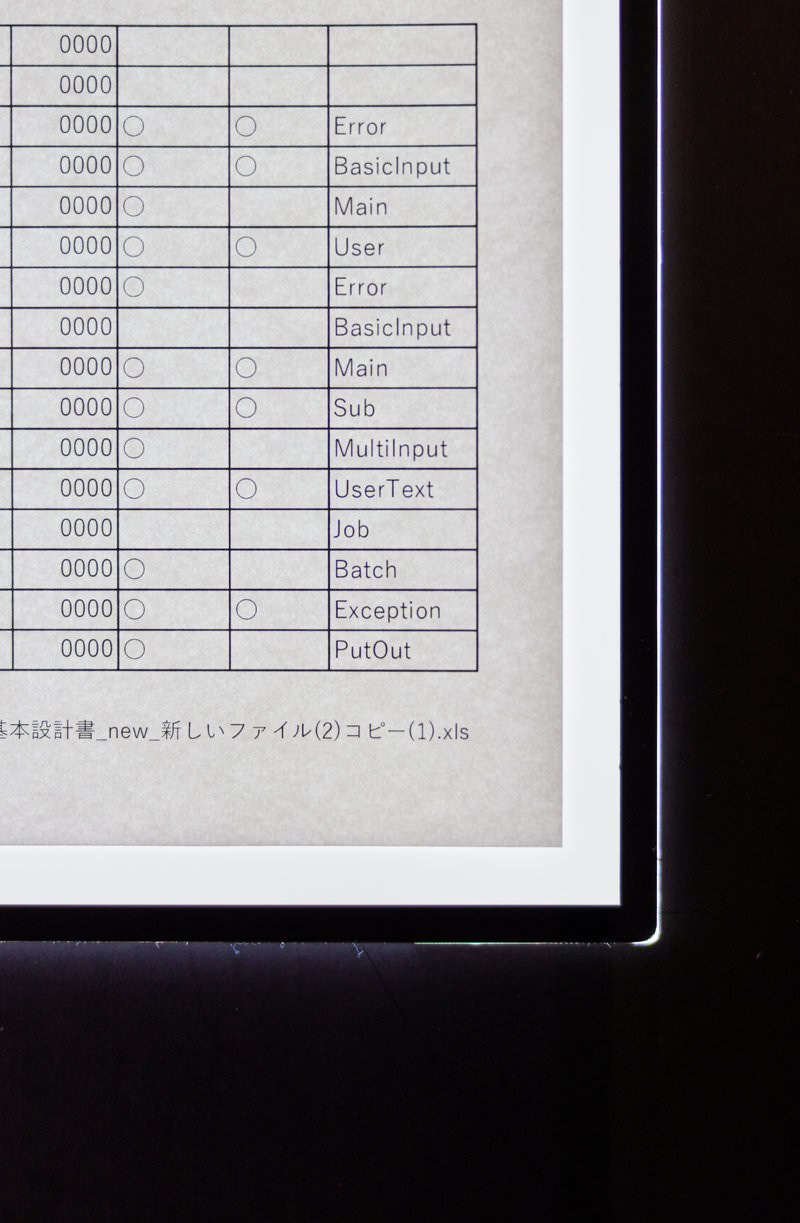「業務委託と派遣のどちらを選ぶべき?」
「業務委託と派遣の違いを知りたい」
とお悩みの方へ向けて、業務委託と派遣の違いについてまとめました。
「業務委託」と「派遣」には細かな違いがあり、企業の状況や目的によって最適な選択は異なります。
本記事では、業務委託と派遣それぞれの特徴や違い、メリット・デメリットについて詳しく解説し、どのような場合にどちらを選択すべきかについてもご提案します。
業務委託と派遣の違いとは

業務委託と派遣は、外部人材活用の代表的な形態です。
直接雇用ではないことは共通していますが、法的な位置づけや実務上の取り扱いが異なります。以下、主要な違いについて詳しく見ていきましょう。
1.契約形態
業務委託は「請負契約」または「準委任契約」に基づく契約形態であり、成果物やサービスの提供を約束する契約です。
請負契約では、受託者(フリーランスや企業)が成果物の完成を約束し、報酬を受け取ります。
一方、準委任契約では、特定の業務遂行を委託するものの、成果の完成を保証するわけではなく、業務の遂行自体が目的となります。
派遣は「労働者派遣契約」に基づき、派遣元企業が雇用する労働者を派遣先企業で働かせる契約形態です。
派遣社員の雇用契約は派遣元企業と結ばれており、派遣先企業は指揮命令のみを行います。
労働基準法や労働者派遣法が適用されるため、雇用の安定や労働者の権利保護が重視されます。
2.業務の指揮命令権
業務委託では、発注者(委託元企業)は業務の進め方について細かい指示を出すことはできません。
受託者は独立した事業者として業務を遂行するため、業務の進め方やスケジュール管理などは基本的に受託者の裁量に委ねられます。
ただし、契約内容によっては納期や品質基準を定め、それに基づいた業務遂行が求められます。
一方派遣では、派遣先企業が派遣社員に対して直接指揮命令を出すことが可能です。
勤務時間の管理、業務内容の指示、作業手順の決定など、一般的な雇用契約と同様の管理が行われます。
派遣社員は派遣先の社員と同じように働くものの、給与の支払いや雇用契約は派遣元企業が管理します。
3.社会保険料の負担
業務委託では、受託者が個人事業主または法人として活動するため、社会保険料は受託者自身が負担します。
個人事業主の場合は国民健康保険や国民年金に加入する必要があり、雇用保険は適用されません。
法人の場合は、法人として社会保険に加入するかどうかを決定することになります。
委託元企業は社会保険料を負担する義務がないため、委託料のみを支払えばよいというメリットがあります。
一方、派遣社員の場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)は派遣元企業が加入手続きを行い、保険料の負担をします。
派遣元企業はこれらの費用を派遣料金に含めて派遣先企業に請求するため、派遣先企業が直接負担するわけではありません。
4.責任の所在
業務委託では、成果物の品質や納期に関する責任は受託者が負います。
契約内容に基づき、成果物の不備や納期遅延が発生した場合、受託者が修正対応を行う義務があります。
特に請負契約の場合、成果物の完成責任があるため、発注者が納得する品質のものを納品することが大切です。
一方、派遣では、派遣社員の業務遂行に関する最終的な責任は派遣先企業にあります。
ただし、労務管理責任は派遣元企業が負っており、例えば派遣社員の労働時間管理や社会保険の手続きなどは派遣元企業が行います。
派遣社員が業務上のミスをした場合、派遣元企業と派遣先企業の責任の所在が問題となることもあり、契約内容に応じた対応が必要です。
業務委託のメリット

業務委託は、特に専門性の高い業務や、一時的なプロジェクトの遂行に適しています。
人材活用の幅を広げ、経営効率を高められるでしょう。
①専門的なスキルを持つ人材を活用できる
業務委託では、特定の分野で高い専門性を持つフリーランスや専門企業のサービスを活用できます。
たとえば、下記の専門的な業務において、必要な時に必要なスキルを持つ人材やチームを確保できるでしょう。
- システム開発
- デザイン
- マーケティング
正社員として雇用するよりも、高度な専門性を柔軟に活用できる点が大きなメリットです。
②必要な業務のみにコストを集中できる
業務委託では、必要な業務や成果物に対してのみ対価を支払えばよく、固定費を抑えることが可能です。
繁忙期と閑散期の波がある業務や、一時的なプロジェクトなどで特に効果を発揮します。
また、成果報酬型の契約も可能なため、業績に直結した費用対効果の高い人材活用が実現できます。
③雇用期間が限定的
業務委託は、プロジェクトや業務の完了をもって契約が終了するため、長期的な雇用リスクを抱えることがありません。
また、契約更新の判断も比較的自由度が高く、業務量の変動に応じて柔軟な契約管理が可能です。
必要な期間だけ必要な人材を確保できる点は、経営の機動性を高める大きなメリットです。
業務委託のデメリット

業務委託には多くのメリットがある一方で、運用面での課題や長期的な視点でのデメリットも存在します。
①受託者の管理が難しい
業務委託では直接的な指揮命令ができないため、業務の進捗管理や品質管理が難しくなる場合があります。
特に複数の受託者と契約している場合、それぞれの作業状況の把握や調整に手間がかかるでしょう。
また、受託者が社外にいることで、緊急時の対応や細かな修正依頼などにおいて、スムーズなコミュニケーションが取りづらいケースがあります。
②成果物に対して相違が生じやすい
業務委託では、発注者と受託者が契約を結び、特定の業務や成果物の納品を前提に業務が進められます。
しかし、契約で定められた範囲や品質基準について、双方の認識にズレが生じることが少なくありません。
例えば、発注者は「一般的な基準で十分」と考えていても、受託者が「高品質な仕上がりが求められている」と判断し、納期やコストが予定よりもかかるケースがあります。逆に、発注者が期待していたクオリティに達しておらず、追加修正が発生することもあります。
こうした認識のズレは、業務委託が「指揮命令関係のない契約」であることが大きな要因です。
発注者は業務の進め方を細かく指示できず、成果物が完成するまでプロセスをコントロールしづらいため、完成後に「思っていたものと違う」という問題が発生しやすいのです。
③ノウハウやスキルが蓄積されない
業務委託のもう一つの大きなデメリットは、社内にノウハウやスキルが蓄積されにくい点です。業務委託では、特定の業務を外部の専門家に依頼するため、業務の遂行や知識が社内で共有されにくくなります。
例えば、システム開発やマーケティング業務を外部委託した場合、成果物として完成したシステムや施策は社内に残りますが、その過程で得られた知見やノウハウは基本的に受託者側に蓄積されます。
次回以降の改善や最適化を行う際、発注者側にその知見がないため、毎回新たな委託先を探したり、同じ内容を説明したりする手間が発生します。
業務委託が向いている業務

業務委託は、専門性が高く、成果物が明確に定義できる業務に特に適しています。
具体的には、下記の業務が挙げられます。
- システム開発
- Webサイト制作
- マーケティング戦略の立案
- 経理・会計業務
- 法務相談
上記のような、専門的なスキルや資格が必要な業務が該当します。
また、プロジェクト単位で完結する業務や、繁忙期に一時的に発生する業務なども、業務委託との相性が良いでしょう。ただし、
日常的な運営業務や、社内の連携が必要な中核的な業務については、派遣や正社員での対応を検討する方が望ましいです。
派遣のメリット

派遣社員の活用は、人材リソースを迅速かつ効率的に確保できる手法として多くの企業で採用されています。即戦力となる人材の確保や、繁忙期の人員補強において高い効果を発揮します。以下、派遣活用の主なメリットについて解説します。
①スキルを持った人材を活用できる
派遣会社は多くの登録者の中から、企業の要望に合致したスキルや経験を持つ人材を選定し、提供します。
一般事務や営業事務、データ入力などの業務では、即戦力となる人材を短期間で確保できるでしょう。
また、派遣会社による事前研修やスキルチェックが行われているため、一定水準以上の業務品質を期待できます。
②人材確保のコストを削減できる
採用活動にかかる時間や費用を大幅に削減できることが、派遣活用の大きなメリットです。
求人広告の掲載、面接の実施、雇用条件の交渉といった採用工程を派遣会社が担当するため、企業側の負担は軽減されます。
また、研修期間中の人件費や教育コストも抑えられるため、即戦力の確保という点でコストパフォーマンスに優れています。
③労働管理の負担を軽減できる
派遣社員の労務管理の主な責任は派遣会社にあるため、企業側の管理負担を軽減できます。
社会保険の手続きや給与計算、勤怠管理などの実務は派遣会社が行い、企業は業務の遂行に専念できるのです。
また、急な欠勤や休暇取得時の代替要員の手配なども、派遣会社のサポートを受けることが可能です。
派遣のデメリット

派遣活用にはさまざまなメリットがある一方で、制度上の制約や運用面での課題も存在します。以下で解説していきます。
①定着率が低い可能性がある
派遣社員は比較的転職率が高く、長期的な人材の定着が難しい傾向にあります。
キャリアアップを目指して転職するケースや、より良い条件の仕事に移って去っていくのです。
そのため、業務の引継ぎや新しい派遣社員の教育に時間とコストがかかる可能性があり、業務の継続性や効率性の低下が懸念されます。
②3年ルールにより長期間の雇用には制約がある
労働者派遣法の規定により、同一の派遣労働者を同一の職場で継続して受け入れることができる期間は、原則として最長3年までとされています。
3年ルールにより、熟練した派遣社員であっても一定期間後には交代が必要となり、業務の継続性や専門性の維持が困難になる可能性があります。
③業務内容が一部制限される場合がある
労働者派遣法により、製造業務や建設業務、港湾運送業務など、一部の業務については派遣が制限されています。
また、派遣社員に従事させることができる業務の範囲も法律で定められており、企業が望む業務すべてを派遣社員に任せられるわけではありません。
派遣が向いている業務

派遣は、下記のような比較的定型的な業務や、短期間で習得可能な業務に適しています。
- 一般事務
- 営業事務
- 受付業務
- データ入力
また、繁忙期の人員補強や産休・育休の代替要員など、一時的な人材需要への対応にも有効です。業務内容が明確で、指示系統が確立されている職場では、派遣社員の活用がスムーズに進みやすいといえるでしょう。
業務委託と派遣どちらを選べば良い?
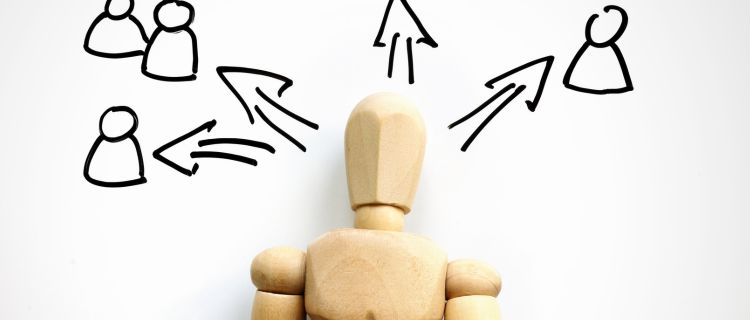
選択の基準は、業務の性質と企業のニーズを中心に検討します。
専門性が高く、成果物が明確な業務は業務委託が適しています。
一方、継続的なサポートが求められる業務や、社内での調整やコミュニケーションが頻繁に発生する業務は派遣が向いています。
コスト面や管理体制、期間の制約なども考慮に入れ、総合的に判断することが大切です。
『CLOUD BUDDY』なら業務委託のデメリットを気にせず活用できます!
「外部リソースを活用したいけど、どう依頼したらわからない」
そんな方は、『CLOUD BUDDY』がおすすめです。
『CLOUD BUDDY』は、業務の効率化を図るためのクラウド型業務整理および業務処理サービスで、専門知識を持つ人材リソースを外注で活用できます。
通常の業務委託では、フリーランス人材のマネジメントや成果物の品質管理が難しく、さらに業務のノウハウが社内に蓄積されにくいという課題があります。
『CLOUD BUDDY』では、専門知識を持つコンサルタントがフリーランス人材のマネジメントを行い、業務の可視化から成果物の品質管理まで徹底サポートすることで、発注者と受託者の認識のズレを防ぎ、期待通りの成果物を得ることができます。
また、業務フローの可視化や手順書の作成を支援することで、ノウハウを社内にしっかりと蓄積し、業務の属人化を防ぎながら継続的な業務改善を可能にします。
専門性が必要な業務を任せたいが正社員を抱えるのは難しい、教育コストをかけられないといった企業の課題に対し、柔軟なソリューションを提供し、業務の効率化を後押しします。
人手不足を解消して業務を円滑に進めよう
業務委託と派遣は、契約形態や責任の所在、社保負担の有無が異なります。
業務委託は、ITやマーケティングのような専門的な知識が必要な業務、プロジェクトベースの業務アサインに向いています。
派遣は、製造業の繁忙期やイベントスタッフなど一時的に人手が必要な場合や、オフィスでの一般的な事務作業や軽作業に向いています。
自社の状況や目的を明確にし、それぞれの特徴を理解した上で、戦略的に外部人材を活用すると、効率的な業務運営を実現できるでしょう。